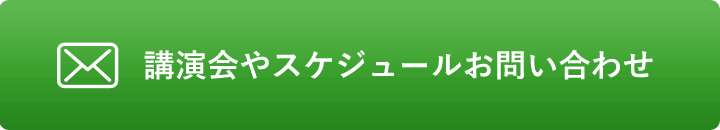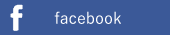![]()
戦地からの愛
—伊藤半次の絵手紙が語る平和のメッセージ—
![]()

はじめに
 今年は戦後80年です。先の大戦では、多くの尊い命が失われ、数えきれないほどの悲劇がありました。
今年は戦後80年です。先の大戦では、多くの尊い命が失われ、数えきれないほどの悲劇がありました。
愛する家族や親しい友人たちと別れて戦地に赴き、最期の一瞬まで懸命に生き抜き、散っていった多くの人たちがいました。
私の祖父 伊藤半次も、1945(昭和20)年に沖縄戦で32歳の若さで戦死しました。
私が祖父の手紙に出会ったのは、2003(平成15)年5月に祖母が他界した時のことでした。祖母が亡くなる間際に父に託したもので、初めて目にした時の衝撃は今でも忘れられません。その父も、この手紙が平和を伝える貴重なメッセージとして生き続けることを願いつつ私に託し、2013(平成25)年9月に他界しました。
幸い、祖父の手紙は家族や友人・知人の元に届きましたが、「硫黄島の手紙」のように戦地から送ることすらできなかったもの、輸送中に海に沈んだものなど、様々な理由で届かなかった数えきれない想いがあったことを想像すると、これだけの手紙が残されていることが奇跡のようにも思えます。
同時に、今この時代、当たり前のようにメールや携帯電話で簡単に思いを伝えることができ、家族や友人など大切な人と過ごせることがなんとも有り難いことなのだと改めて感じています。
辛くとも明るく生きよう、必ず生き残って家族の元に帰りたい・・・・
祖父 伊藤半次の絵手紙は、今を生きる私たちに平和のメッセージとして色々なことを語りかけてくれます。
伊藤半次の絵手紙
福岡市博多区で老舗の提灯店を営んでいた伊藤半次は、1945(昭和15)年に旧日本陸軍に入隊し、その後満州に出征、戦地に赴きます。
兵士として戦地に行った後も残された家族に対して愛情あふれる絵や手紙400通も送り続けました。
戦争当時、戦地と自国との間に取り交わされる郵便物は、一部を除いて無料で取り扱われていました。当時は、当たり前のように秘密保持のため文面が厳しく検閲され、反戦的な内容や部隊に関係するものはすべて削除されました。現在地などは〇〇と伏せられ、発信元の住所も地名ではなく部隊名で届けられました。もちろん祖父の手紙も意図的に〇〇と伏せられたものもありますが、なぜ異国の戦地から、これほどまでたくさんの書簡を送ることができたのか首を傾げるしかありません。しかも、絵手紙には色鮮やかに描かれた「妻が風呂に入っている絵」「異国の子供と日本の子供が握手をしている絵」などもあり、チェックされて消された手紙(形跡)がほとんどないのです。後に、手紙の内容から「上官に近い立場だったこと」「どの手紙の絵も文章もつとめて明るく描いている」「宛名の書体を意図的にかえている」「半次、喜平(僖苹)と名前を使い分け」「妻にしかわからない二人だけのサインを用いる」など、機転が利く人だったことがわかり、いろんな工夫をしていたのがよかったのかもしれません。
しかし、沖縄から送られてきた手紙は、わずかに3 通。それも既製の絵葉書に切手を貼ったもので、それまでの明るい絵などもなく、慌ただしく書いたと見られる筆跡で、家族に無事を知らせる内容などでした。満州から多くの手紙を送り続けた祖父からの手紙は、1944(昭和19)年11 月に沖縄から私の父(次男允博)宛に届いた手紙が最後となり、半次の消息は途絶えます。

祖父の足跡をたどる
「あなたのおじいちゃんは、私たち家族を家(福岡)から近いところで守りたいからと言って沖縄に行ったのよ!」
私が祖父について知っているのは、子供の頃たった一度だけ祖母が話してくれた、この言葉だけでした。私の父(允博)は、父親(半次)から抱かれた記憶が全くなかったので、半次が戦争に行って戦死するまで、一緒に過ごすことができなかったと思っていましたが、1941(昭和16)年1月28 日に父(允博)が誕生してから約半年もの間、父親(半次)と一緒に過ごしていた時間があったことが、残されていた軍歴資料から後に判明しました。残念ながら、父はこの事実を知らないまま2013(平成25)年に他界してしまいました。
父の死から間もなく、私は、沖縄からの手紙3 通と、軍歴資料の情報などをもとに、祖父の足跡をたどる旅をはじめることを決意し、さっそく行動に移したのでした。死没者原簿に記された「沖縄本島小渡」は、現在の沖縄の住所には存在しない地名でしたが、その地には、祖父が所属した部隊慰霊碑があり、様々な調査、多くの出会い、当時を知る人たちからの証言などから、祖父の足跡が少しずつ分かってきました。
すでに戦後70 年以上が経過しており、当時の詳細を知ることには限界があると諦めかけた頃(令和1年6 月17 日)、祖父と同じ部隊に所属し戦死した方のご遺族(鐘ケ江静男氏当時92 歳)と福岡縣護国神社の祥月命日祭で偶然出会い、野重23 会(部隊生き残り、ご遺族などで構成。平成6 年に解散)の「野戦重砲兵第23 連隊抄史」「野重23 会々報(最終号)」を翌18 日(半次の戦死から73 年目)に託され、それらの資料から、満州そして沖縄戦の部隊動向が判明しました。残された資料の中には「野戦重砲兵第23 連隊の部隊史を掲載致しましたので、永久に保管して下さいます様に……」との願いが込められていました。沖縄戦で戦死した兵士である伊藤半次の絵手紙を全文書き起こし、足跡をたどってわかったことなどを「伊藤半次の絵手紙 戦地から愛のメッセージ」(集広舎・2021)書籍にまとめ、生涯を閉じた方々の想いを風化させず後世に伝えるため、野重23会々報(最終号)」も原文のままご紹介しました。

未来へのメッセージ
祖父(伊藤半次)が戦地から家族に送り続けた愛情あふれる絵手紙。
絵具や色鉛筆で描かれた色鮮やかな絵手紙の数々には、家族の事を思い浮かべながら想像して描かれた絵、そして駐屯地の四季の移り変わり、異国の人々の暮らしぶり、軍隊生活での出来事や近況などこまめに色んな事を伝えています。どの文面も明るく、描かれた人物にしてもほとんどが笑っており、家族一人一人を思いやり安心させようとしていたのが伝わってきます。しかし、愛する家族と暮らす平穏な日々を夢見ていた半次でしたが、その夢は無惨に打ち砕かれ1945(昭和20)年6月に沖縄で戦死しました。
時は流れ、戦争の時代を生き抜いてこられた方もすでに高齢化し、戦争体験を語り継ぐことが難しくなっています。祖父の伊藤半次が描いた戦地からの絵手紙を通して、今を生きる私たちが、平和を考えるきっかけになるよう、戦地からの絵手紙を「未来へのメッセージ」として企画展を開催したり、様々な場所で講演を行っています。
講演では、祖父(伊藤半次)が戦時中に実際に描いた絵手紙も見ていただき、一人の兵士の絵手紙が、家族や仲間の大切さ、感謝、戦争のむなしさ、残酷さ、平和の尊さなどを考えるきっかけとなり、この先、戦後100年、150年と、平和な世の中が続き、戦争の記憶が思い起こされるたびに、このメッセージを語り継いでいただけたら、これ以上嬉しいことはありません。

![]()
(集広舎・)

父の死をきっかけに祖父の足跡をたどり、沖縄戦の過酷な状況や真実、生々しい証言に直面しながら、祖父の絵手紙や人生を通じて「今を生きる私たちが未来に向かってどうすれば良いのか」「命の大切さ」といったテーマで、小中学校や公民館など、幅広い年代の聴衆に向けて講演活動を行なっており、多くの新聞やテレビでも取り上げられています。著書「伊藤半次の絵手紙(2021 集広舎刊)」
合わせて読みたい記事