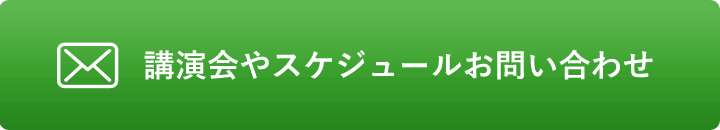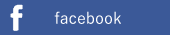![]()
終活の知識を深める
![]()

1、終活とはどのようなものか?
![]()
 私は、これまで企業研修のほか、公的機関、社会福祉協議会、障害者支援施設、生涯学習センターの依頼などで講師をしてきました。ご挨拶のときは、司法書士の名刺を出すことが多いですが、最近では、シュウカツ(就活ではなく終活)という言葉が、当たり前に通じるようになりました。超高齢化社会になり、テレビや新聞でも終活の話題がしばしば取り上げられ、終活の認知度は、急速に高まっていると感じます。
私は、これまで企業研修のほか、公的機関、社会福祉協議会、障害者支援施設、生涯学習センターの依頼などで講師をしてきました。ご挨拶のときは、司法書士の名刺を出すことが多いですが、最近では、シュウカツ(就活ではなく終活)という言葉が、当たり前に通じるようになりました。超高齢化社会になり、テレビや新聞でも終活の話題がしばしば取り上げられ、終活の認知度は、急速に高まっていると感じます。
終活とはどのようなものか、端的に言いますと、お墓に入る準備、死ぬ準備です。しかし、そう言ってしまうとあまりに直接的であり、後ろ向きのイメージでもあります。これでは、高齢者は終活をするモチベーションも上がりませんから、どうにか前向きに考えてみるわけです。そこで私は、終活とは、人生を最後まで、人間的に、自分らしく生きる、あるいは自分らしく死ぬ、そのための準備や活動をすることだと考えます。
2、認知症対策と成年後見など
![]()
 年を取るにつれ、身体的にも精神的にも弱っていく中で、自己の財産や利益、権利を守るというのは、非常に重要です。昔の平均寿命は、せいぜい60歳~70歳前後で、そうであれば、終活はさほど重要なことではなかったかもしれません。しかし、いま私たちは、当たり前に長生きをするようになり、寝たきりや認知症の状態で生き続ける人も多く、そこから死ぬまでの時間は、結構長い道のりといえます。
年を取るにつれ、身体的にも精神的にも弱っていく中で、自己の財産や利益、権利を守るというのは、非常に重要です。昔の平均寿命は、せいぜい60歳~70歳前後で、そうであれば、終活はさほど重要なことではなかったかもしれません。しかし、いま私たちは、当たり前に長生きをするようになり、寝たきりや認知症の状態で生き続ける人も多く、そこから死ぬまでの時間は、結構長い道のりといえます。
この間の財産管理と身上の保護をどうするかについては、誰にとっても悩ましい問題です。主に認知症対策が課題や論点となりますが、現在は、認知症になってから、成年後見(法定成年後見制度)を利用するのが主流です。ただ、そのほかに、任意後見や民事信託の契約など、事前に様々な対策をしておくことも可能なのです。これらの事前対策の制度を有効活用することで、自分の希望に沿った財産管理や身上の保護が実現できるようになります。
3、遺言書とエンディングノート
![]()
親であれば、子供たちのため、お金をのこしてあげたい、という想いが強いでしょう。生前贈与をしたり、あるいは遺言書を作成し、相続争いを避けるなど、財産面での対策をいろいろとやることは重要です。しかし、遺言書の作成はハードルが高く、書こうと思っているけれどもまだ書いていないという人も多いのです。そういう人には、まず、エンディングノートを書くのがおすすめです。
エンディングノートは、かしこまった法律的文書ではなく、単なるメモ帳の扱いで、法的効果はありません。しかし、試しに書ける、気軽に書けるので、エンディングノートは、ちょっとした人気商品となっています。法的事項以外も書けるので、自分の人生を振り返り、想うことや考えていることなどをエンディングノートには自由に書くことができます。

4、おわりに
![]()
終活講座の受講者の年齢はさまざまです。60代以上の方は最も多いですが、働き盛りの中年の方々も、終活に興味を持っていただきたいと考えています。自分の親が70代後半から80代になるといろいろと弱ってくるので、親の終活を支援することが重要になるからです。ぜひ、みなさまには、私の講座を受講し、終活の知識を深めていただきたいと思います。

![]()
(日本実業出版社・新書・ビジネス書・2023/11/10)

株式会社EnsembleFund&Consulting代表取締役。加藤光敏司法書⼠事務所代表。昭和⼥⼦⼤学現代ビジネス研究所研究員。終活のほか、投資に関する講演や執筆もしている。
合わせて読みたい記事