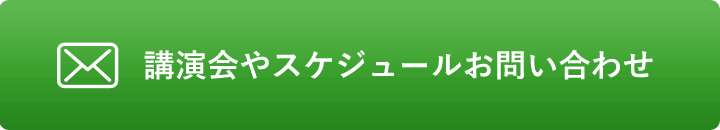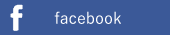![]()
明日から役立つ「常勝営業チームのつくり方」
![]()

「営業本」が現場で役立たない理由とは?
![]()
 営業関連のビジネス書籍いわゆる「営業本」を、お読みいただいたことがあるでしょうか?毎月のように似たようなタイトルの書籍が出版され、書店店頭で代わる代わる平積みにされています。大手企業などでトップ営業として活躍された方々が筆者のこの手の書籍ですが、営業を担当したことのある人ならば、1冊や2冊は購入したことがあるのではないでしょうか。読んでみれば、どれも役に立ちそうなノウハウが満載です。それでありながら、現場で営業の皆さんに「営業本」が役に立っているのかを聞いてみると、参考にはなっても役に立ったという人は本当に少数なのです。それはなぜなのでしょう。
営業関連のビジネス書籍いわゆる「営業本」を、お読みいただいたことがあるでしょうか?毎月のように似たようなタイトルの書籍が出版され、書店店頭で代わる代わる平積みにされています。大手企業などでトップ営業として活躍された方々が筆者のこの手の書籍ですが、営業を担当したことのある人ならば、1冊や2冊は購入したことがあるのではないでしょうか。読んでみれば、どれも役に立ちそうなノウハウが満載です。それでありながら、現場で営業の皆さんに「営業本」が役に立っているのかを聞いてみると、参考にはなっても役に立ったという人は本当に少数なのです。それはなぜなのでしょう。
その回答は、私がお手伝いしてきた多くの企業で見てきた、いわゆるトップ営業たちの共通した才にありました。それはすなわち、自己管理能力です。彼らは皆、自分なりの営業方法を決め、毎月計画的な活動を遂行するという、自己を律して自ら定めたやるべきことをしっかりやり抜く自己管理力の持ち主だったのです。たとえ「営業本」からすぐれた営業ノウハウを吸収しようとも、それを計画的に遂行することができなかったり、目先の成果が上がらないからと諦めてしまったり、やり方を変えてしまったりということでは、せっかくの“黄金ノウハウ”も成果にはつながらないのです。

この事実は裏を返せば、世の営業担当者の大半は自己管理が十分にはできていない、ということでもあります。担当者の自己管理が不十分であるのならば、他人管理に委ねる以外にありません。となれば営業力強化に悩む企業がやるべきことは、自社における営業管理の手法をしっかり確立し、管理者がそれを担当者一人ひとりに対して実行する、すなわち担当者に伴走することなのです。営業力強化に向けてやるべきことは、それに尽きると言っても過言ではありません。
営業チームを成功に導く管理の秘訣
![]()
私は元々、営業エリア内に自社の倍以上もの都市銀行の支店がひしめいていた金融激戦地域、神奈川県を地盤とする地方銀行に勤務していました。営業担当者としての経験を下地に、最終的には支店長として自店の営業管理強化に励みました。結果、個々の営業担当者を指導しつつ皆の実績を積み上げ、約1年で常勝の営業チームに育て上げました。自社よりも規模が大きく、ネームバリューもあり、商品開発力でもまさっている複数のライバルに対し、自力で培った「営業力」を武器に連戦連勝のチームを作り上げたのです。
私の営業活動のベースになったのは、若い頃に新卒採用リクルーターとして、自社を第一志望ではなかった大量の有名大学在学生を寝返り入社に導いた採用活動体験でした。そのあたりの経緯と営業管理に転化した具体的手法は講演・セミナーで詳しくお話ししていますが、一言そのポイントを申し上げておくと、営業管理の「仕組み」と「仕掛け」そして「具体的管理手法」を明確化して、それを管理者と担当者が共有しつつ前に進んでいく、ということになります。また営業の世界では、「三大ダメ営業」と名付けている営業担当が陥りやすいエラー活動があり、その撲滅もまた営業力強化には重要です。
 ダメ営業のひとつ目は、「御用聞き営業」です。定期的に取引先を訪問して担当者と歓談し、最後に「何か御用はありませんか?」とニーズの有無を確認する営業です。昭和の高度成長期は、黙っていても注文が途切れない幸せな時代で、営業担当は世間話の類の雑談だけして「御用」の有無を聞くというスタイルが全盛を極めました。バブル経済の崩壊以降、低成長の時代に移行し、「御用聞き営業」は徐々に姿を消していきましたが、令和の今も「営業はお前自身を売り込むことだ!」「当社の良き協力者となる客をつくれ!」などと部下に宣う上司は、御用聞き営業養成管理者の悪臭が強く漂っており要注意です。
ダメ営業のひとつ目は、「御用聞き営業」です。定期的に取引先を訪問して担当者と歓談し、最後に「何か御用はありませんか?」とニーズの有無を確認する営業です。昭和の高度成長期は、黙っていても注文が途切れない幸せな時代で、営業担当は世間話の類の雑談だけして「御用」の有無を聞くというスタイルが全盛を極めました。バブル経済の崩壊以降、低成長の時代に移行し、「御用聞き営業」は徐々に姿を消していきましたが、令和の今も「営業はお前自身を売り込むことだ!」「当社の良き協力者となる客をつくれ!」などと部下に宣う上司は、御用聞き営業養成管理者の悪臭が強く漂っており要注意です。
ふたつ目のダメ営業は、「押し売り営業」です。「押し売り」と聞くと、強引な営業姿勢を思い浮かべますが、すぐにセールスしたがる営業はすべて「押し売り営業」です。営業には既存先営業でも新規先営業でも、セールス以前に踏むべきステップが存在します。そのステップは商材によって、入口から成約に至るまで1時間で終了するものもあれば、1年以上かかるものもあります。しかし基本は、どれも同じステップを踏むことで成約の確率が圧倒的に高くなるのです。相手と会った途端、「新製品が出たので、お時間ください」などというのは体のいい「押し売り営業」であり、管理者の指導が間違っているのです。
三つ目は、「安売り営業」です。競合が登場した途端に、とにかく相手よりも1円でも安い価格を提示して、成約に至らせようとする営業スタイルです。営業活動が単に安さを競うものならば、今時は人的コストのかからないネット営業が最強でしょう。しかし、ネット全盛の時代にあってなおリアル営業が無くならないのは、価格ではないところに人的営業の存在価値があるからに他なりません。安易な値引き営業を容認する管理者の下では、営業力のある営業担当は決して育ちません。自分たちの営業価値は、価格競争とは別のところにあるという営業スタイルを確立することが重要なのです。
 このような「ダメ営業」を生まないためにも必要なことが、しっかりとした営業管理方針と具体的な管理手法なのです。私が構築した「仕組み」「仕掛け」「具体的管理手法」からなる独自の営業セオリーに基づく営業管理ノウハウは、業種を問わず、対法人ビジネス、対個人ビジネスも問わず、既存先営業、新規営業も問わず有効です。セオリーに忠実に活動していただきさえすれば、確実に実績を積み上げる営業チームを作り上げることができると、約20年のコンサルティング経験が実証しています。
このような「ダメ営業」を生まないためにも必要なことが、しっかりとした営業管理方針と具体的な管理手法なのです。私が構築した「仕組み」「仕掛け」「具体的管理手法」からなる独自の営業セオリーに基づく営業管理ノウハウは、業種を問わず、対法人ビジネス、対個人ビジネスも問わず、既存先営業、新規営業も問わず有効です。セオリーに忠実に活動していただきさえすれば、確実に実績を積み上げる営業チームを作り上げることができると、約20年のコンサルティング経験が実証しています。
とび抜けた営業担当者を育てることが、私の営業管理手法の目的ではありません。抜けた成績は必要なく、全員が着実に目標を達成できるようになることを唯一の目標としています。実績抜群のトップ営業がいることは、むしろリスクでもあるからです。その彼が突然抜けてしまうこともあるわけで。力のある営業担当であれば、その力量を活かして今よりも処遇のいいところへと転職するケースも多く、トップ営業が突然抜けてしまい右往左往した会社をいくつも見ています。営業担当者全員が、しっかり目標クリアできるレベルで長く共存する、そんな営業チームがリスク管理の観点からも最強と言えるのです。
強く申し上げておきたいことは、営業には確固たるセオリーがあるということです。すなわち、担当者の営業への向き不向きはほとんど関係なく、セオリーさえ身に付けさせてそれをしっかり管理者が伴走するならば、誰でも目標を達成するレベルの実績はあげられるようになるのです。それまで営業には不向きと思われていた担当者が、しっかり実績を積み上げられるようになった姿を、私はたくさんこの目で見てきています。
冒頭にも触れたように、私は「営業本」が現場のお役に立てないことを知っているので、自己の経験・ノウハウを書籍にはしません。その代わりに、営業チーム強化、個々の営業力向上でお悩みの経営者、管理者の方々に、目から鱗(うろこ)の話をお聞かせしています。明日から役立つ営業力強化をテーマとした講演へのお声掛けを、心よりお待ちしております。

![]()

1959年東京生まれ。開成高校、東北大学卒。銀行に入るも支店長職をひと区切りとして円満退社。「経営コンサルタント 兼 新興市場企業役員 兼 事業会社社長」として独立した。
企業コンサルティングの専門は、人と組織のコミュニケーション。営業にも精通している。
合わせて読みたい記事